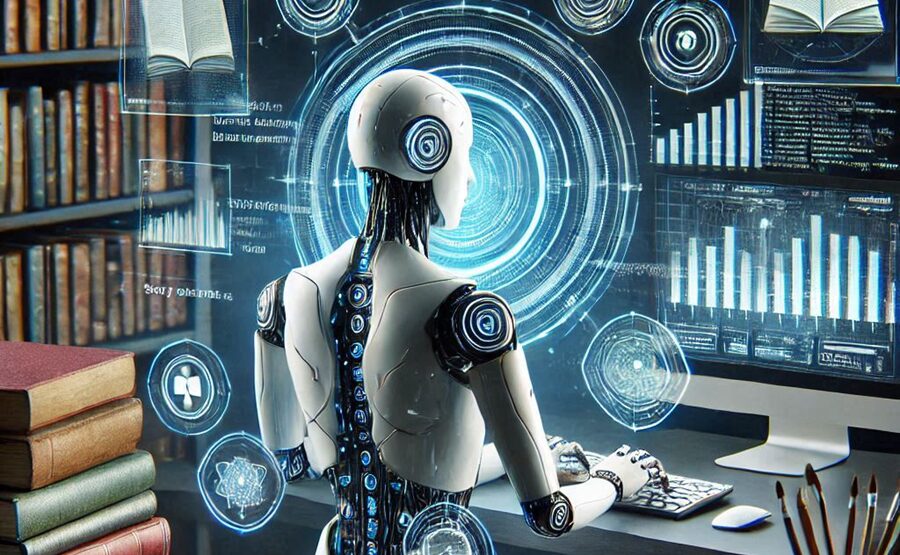生成AIの進歩はすごい!ということで、Googleの生成AI「Gemini2.0 Flash Experimental」に短編SF小説を作ってもらったら、結構面白いものができたので驚きました。
2回ほど修正指示を行い、つじつまをあわせたりした程度でこの出来です。
タイトル:光の彼方からの囁き
第一章:異質な邂逅
見慣れたはずの自室の風景が、その瞬間、異質な空間へと変貌を遂げた。窓から差し込む夕焼けのオレンジ色が、いつもより幾分か不気味に、かずまの部屋を照らしていた。大学生の彼は、レポートの締め切りに追われ、机に向かっていた。キーボードを叩く指が止まったのは、背後から感じた異様な気配のせいだった。振り返ると、そこに信じがたいものが立っていた。
それは人間のような形をしていたが、どこか根本的に異なっていた。身長は2メートルを超え、細身でありながら、その体躯からは想像を絶する力が感じられた。肌は白く、光を反射しているようだった。顔立ちは整っているが、表情は一切なく、まるで彫刻のようだった。服装は、身体にぴったりとフィットした、光沢のある白いスーツのようなものだった。
かずまは言葉を失った。幽霊か、あるいは夢を見ているのかと思った。しかし、その存在感はあまりにも現実的で、否応なく現実を突きつけてきた。使者は、部屋の中央、本来ならば誰もいないはずの空間に現れたのだ。
「…これは、予想外の遭遇だ」
その存在は、静かで落ち着いた声で話しかけてきた。言葉はかずまの知る日本語だったが、どこか機械的な響きがあった。その声には、驚きとも戸惑いともつかない、微妙なニュアンスが混じっていた。
「私は上位層世界から来た。本来、この場所にあなたのような存在がいるはずではなかったのだが…」
使者は、周囲をゆっくりと見回した。その視線は、かずまを通り越し、部屋の奥の壁を見ているようだった。
「上位層世界とは、あなたたちの世界とは異なる次元に存在する世界だ。あなたたちの世界は、私たちが『下位層』と呼ぶ世界の一つに過ぎない」
使者は、まるで独り言のように呟いた後、かずまに向き直った。
「…これも、何かの縁かもしれない」
使者はそう言うと、先ほどまでの戸惑いを消し去り、淡々と語り始めた。上位層世界は、光速を超越した物理法則が支配する世界であり、人類の知覚では捉えられない領域にあるという。時間や空間といった概念は、上位層世界では意味をなさない。使者の姿は、人類の世界に適応するための仮の姿であり、上位層世界における本来の姿は、人類の理解を超越したものだという。
「私たちの世界は、深刻なエネルギー不足に陥っている。そして、調査の結果、あなたたちの世界が豊富なエネルギー源であることを突き止めた」
かずまは使者の言葉の意味を理解しようと必死だった。上位層世界がエネルギーを得る?それは一体どういうことなのだろうか?
「あなたたちの世界からエネルギーを得ることで、私たちの世界は救われる。しかし…」
使者は言葉を区切った。その無表情な顔に、かすかな変化が見えた気がした。
「あなたたちの世界は、宇宙全体を含め、消滅する」
かずまは息を呑んだ。消滅?自分たちの世界が?宇宙が?そんなことがあり得るのか?恐怖と混乱が彼の心を支配した。しかし、彼は必死に冷静さを保とうとした。
「消滅…?そんな、それではあまりにも…!他に方法はないのですか?私たちの世界を救う方法はないのですか?」
かずまは使者に詰め寄った。かすかな希望にすがりつくように、必死に訴えた。
使者は静かに首を横に振った。
「上位層世界の存続は、絶対の命題だ。あなたたちの世界は、私たちにとっては取るに足らない存在に過ぎない。他に方法はない」
「そんな…!それでは、私たちはただ滅びるのを待つしかないのですか?何もできないのですか?」
かずまは絶望的な気持ちで使者に問いかけた。
「あなたたちは、何もできない。これは、上位層世界の決定事項だ。覆すことはできない」
使者の言葉は冷酷だった。しかし、かずまは諦めなかった。
「上位層世界には、時間や空間の概念がないと言いましたね?ならば、過去に遡って、エネルギー不足になる前に手を打つことはできないのですか?あるいは、別のエネルギー源を探すことはできないのですか?私たちに、何かできることはないのですか?」
かずまは必死に食い下がった。使者の言葉の矛盾点を突こうとした。
使者は、わずかに間を置いてから答えた。
「時間や空間の概念がないと言ったのは、あなたたちの理解する時間や空間とは異なるという意味だ。因果律は、上位層世界にも存在する。過去を変えることは、上位層世界の法則に反する。そして、あなたたちにできることは、何もない」
使者の言葉は、かずまの最後の希望を打ち砕いた。彼は、ただ茫然と立ち尽くすしかなかった。
「これ以上の接触はない。あなたたちがどう生きようと、それはあなたたちの自由だ」
そう言い残すと、使者の身体は光の粒子となって消えていった。部屋には、夕焼けのオレンジ色が、以前と変わらず差し込んでいた。しかし、かずまの世界は、永遠に変わってしまった。
第二章:過ぎ去りし日々の残像
50年の歳月は、かずまの身体を確実に老いさせていた。70歳を超えた彼は、白髪交じりの老人となり、顔には深い皺が刻まれていた。しかし、彼の記憶は鮮明だった。50年前のあの日、自室で使者と出会った日のことを、まるで昨日のことのように覚えていた。
夕焼けのオレンジ色を見るたびに、かずまはあの日のことを思い出す。使者の姿、冷酷な言葉、そして世界の終末という宣告。彼は50年間、この記憶に囚われながら生きてきた。
かずまは自室の窓辺に立ち、夕焼け空を見上げていた。50年前と変わらぬ光景だが、彼の心境は大きく異なっていた。
彼は50年間、常に「明日世界が終わるかもしれない」という意識を持って生きてきた。そのため、彼は常に全力投球であり、妥協を許さなかった。その結果、彼の会社は競合他社を圧倒し、彼は若くして億万長者となった。
しかし、富を得ても、彼の心には常に虚無感が漂っていた。明日世界が終わるかもしれないのに、お金持ちになったところで何の意味があるのだろうか?彼は常にそう自問自答していた。
彼は過去を振り返った。大学時代、使者と出会う前は、将来のことを漠然と考えていた。良い大学に入り、良い会社に就職し、普通の人生を送る。それが彼の描いていた未来だった。
しかし、使者との出会いが、彼の人生を大きく変えた。彼は、いつ終わるかわからない世界で、精一杯生きることを選んだ。その結果、彼は成功を手に入れたが、同時に、心の奥底には常に不安と虚無感がつきまとっていた。
世界はまだ終わっていない。彼は50年間、いつ終わるかわからない世界に怯えながら生きてきた。
彼は、使者の言葉を思い出した。「あなたたちの世界は、私たちにとっては取るに足らない存在だ」。上位層世界は、彼らの存在など気にも留めていないのかもしれない。あるいは、エネルギーを得る方法が変わったのかもしれない。
かずまは、明日も世界はあるのだろうか?と自問自答した。答えはわからない。しかし、彼は明日も生き続けるだろう。たとえ明日世界が終わるとしても、今日まで精一杯生きてきたように、明日も精一杯生きるだろう。それが、彼が使者との出会いから得た唯一の教訓だった。
彼は、過去の出来事を回想する中で、使者との問答を何度も反芻した。もし、あの時、別の質問をしていれば、何か違っていたのだろうか?もし、上位層世界の事情をもっと深く探ることができていれば、何かを変えられたのだろうか?
しかし、今となっては、全ては過ぎ去ったことだ。彼は、残された時間を、どのように生きるかを考えるしかない。明日も世界があることを願いながら、彼は静かに目を閉じた。